収入(売上)の計上時期
法人税法や所得税法のルール
今回の記事は顧問税理士を雇ってない個人事業主様や法人経営者様向けに、
いわゆる収入(売上)の「期ズレ」について、税務調査の観点より専門税理士が簡単にご説明いたします。
私の税務調査専門税理士事務所に相談に来られる個人事業主様や法人経営者様のうち、
80%以上の方は銀行の預金通帳の入金欄を見て収入を計上されているように感じます。
そうすると、昨年分であれば令和6年1月から令和6年12月までに入金された金額の合計額が、
法人や個人事業主における令和6年分の年間収入となっています。つまり入金時期を基準にしているわけですね。
しかし残念ながら、所得税法上も法人税法上もこの処理は正しくないのです。
税法上は、入金が何月なのかは関係なく、
例え未入金だとしても、令和6年1月から令和6年12月までの間に『物を販売したり役務提供を実施した金額の合計』が、法人や個人事業主における令和6年分の年間収入となるのです。

期ズレは税務調査官の定番の指摘事項
もう少し具体的な例で見てみましょう。
法人又は個人事業主とその得意先である佐藤商店(月末請求・翌月末入金)との取引を例にします。
佐藤商店に対し令和6年12月分の販売が80万円あったとします。そして、
◆令和6年12月分の請求書を令和7年1月4日に郵便にて佐藤商店に発送
◆令和7年1月31日に佐藤商店から80万円が無事入金がされた
この場合、佐藤商店に対する収入80万円はあくまで令和6年12月分の販売なので、
法人や個人事業主が申告する際は、令和7年分ではなくあくまで令和6年分の確定申告で収入(売上)計上する必要があるのです。
実際の入金は令和7年1月末なので、ほとんどの個人事業主や法人経営者の方は令和7年分の確定申告で収入として計上しているのが実情です。
もちろんこのレベルであれば重加算税の対象とはなりませんが、
税務調査官からは『佐藤商店に対する収入80万円をプラスして令和6年分の修正申告書を提出してください』と言われます。
この指摘事項は『期ずれ』と言われるものであり、とりわけ顧問税理士を雇ってない法人や個人事業主に対する税務調査においては、定番の指摘事項となっています。
税務調査でどう対応すれば良いか?
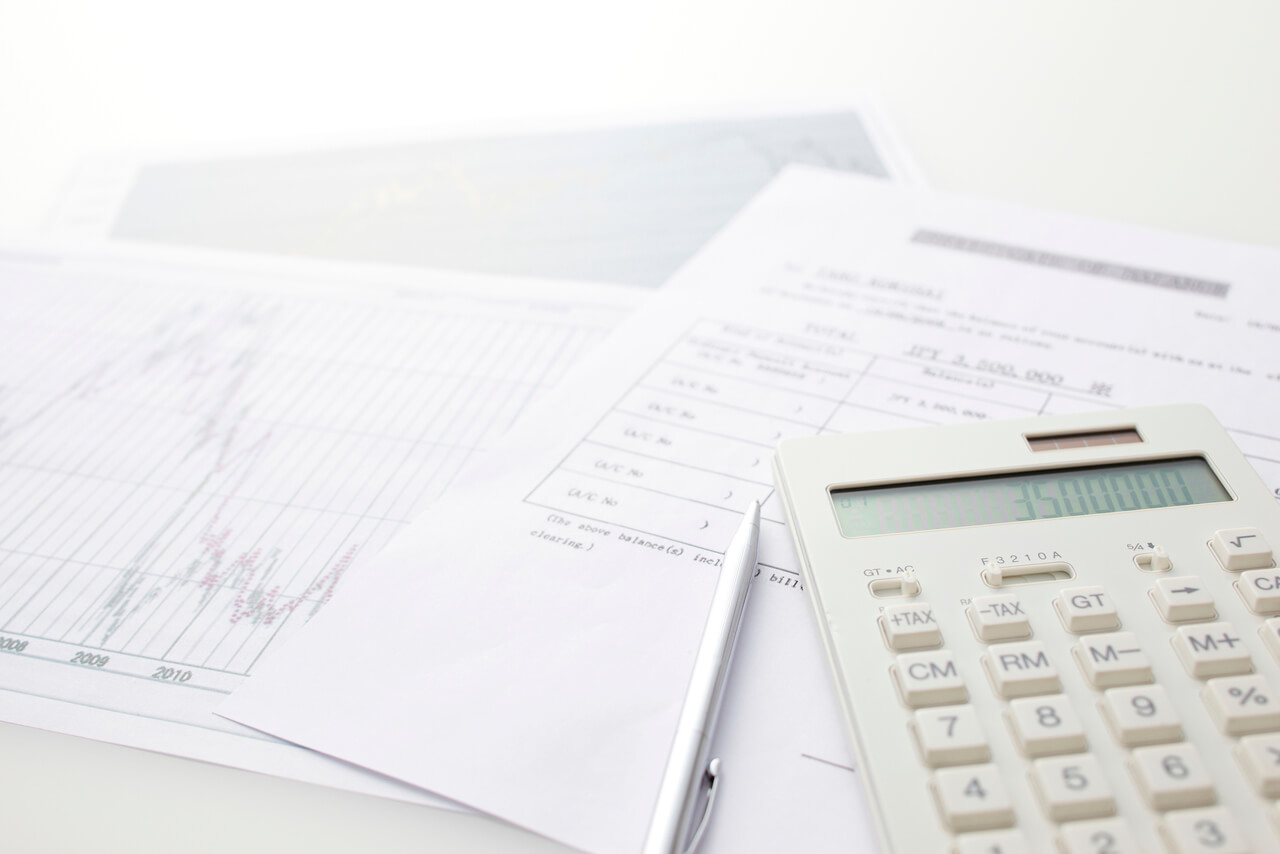
個人事業主に対する税務調査の結果、収入80万円をプラスして所得税の修正申告をした場合のざくっとした税負担額ですが、
〇所得税(10%と仮定)が8万円
〇住民税が8万円
〇消費税(義務がある場合)が8万円
〇国民健康保険税が8万円
〇事業税(義務がある場合)が4万円
の合計額36万円が追徴される計算になります。
実際は上記の他に、過少申告加算税と延滞税も漏れなく付いてきます。
もし顧問税理士を雇っていない個人事業主の方が、税務調査においてこのような指摘を受けた場合には、
『必要経費について追加で認めて貰えるものはないか検討して下さい』と税務調査官に依頼してください。
例えば、個人事業主の外注先である田中工務店からの令和6年12月分の請求額20万円について、
その支払が令和7年1月31日になっていることはないでしょうか?
外注費などの必要経費についても何月に支払ったのかは関係なく、
税法上のルールは、あくまで実際に仕事をやってもらった月の外注費として計上できるのです。
必ず税務調査官に対し、
『田中工務店に対する外注費20万円は令和6年12月分なので、令和6年分の修正申告をする際に外注費20万円を認めてください。』と主張していただきたいのです。
税務調査官が納得すれば、
◆80万円-20万円=60万円
が修正申告書でプラスされる所得金額となりますので、税負担額が大きく変わってくる(減少する)と思います。
財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。
LINE ↓友だち追加↓
税務調査情報をお伝えいたします
お気軽に友だち追加してください
Menu
- 事務所紹介

