個人事業主が申告書を下から作る
今回はいわゆる『下から作られた申告書』について、税務調査専門税理士がご説明いたします。
税務調査必須となる個人事業主の申告書
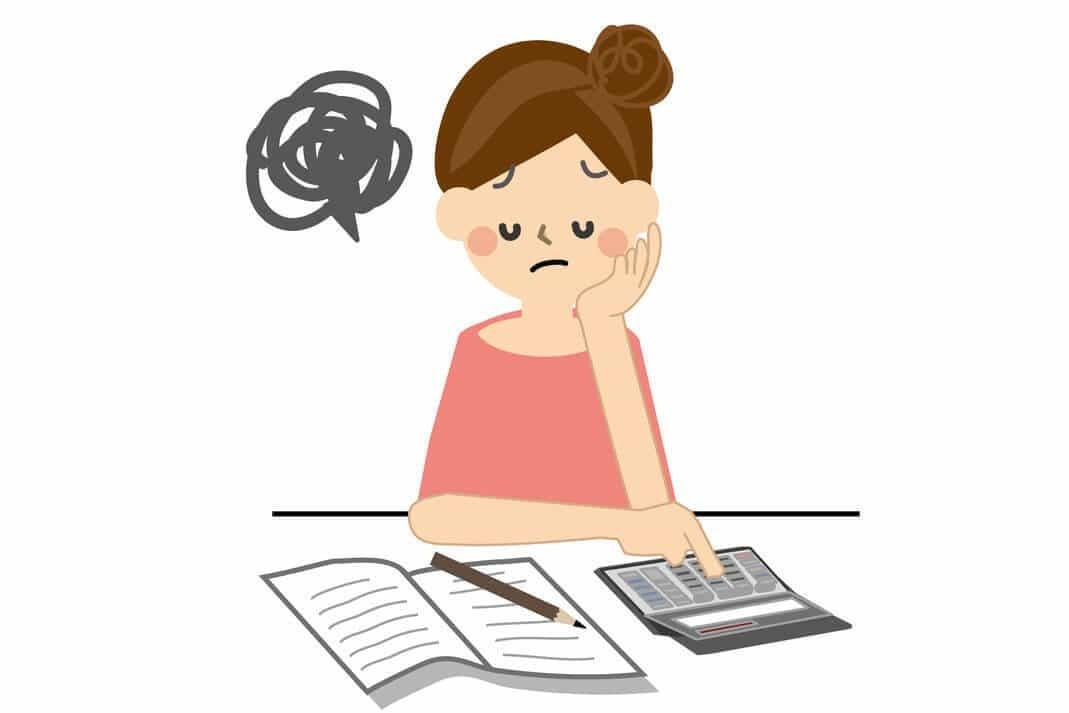
個人事業主が作成する所得税の確定申告書は、まず収入から必要経費を差し引き、
更に扶養控除などの各種所得控除を差し引くことによって納付税額を確定させる、という順序で作成します。
所得税の確定申告書をご覧になっていただければ一目瞭然なのですが、まさに申告書の上から下に向かって作成することになるのです。
個人事業主本人が作成した確定申告書を見ると、わりと多いのが毎年の納付税額が決まって数万円になっている確定申告書です。
私のような税務調査を専門としている税理士がこのような申告書をみると、「この個人事業主の方は、最初に納付税額ありきで申告書を下から作成しているのでは?」とうがった見方をしてしまいます。
サラリーマンと異なり個人事業であれば、景気の良し悪しと共に売上や所得(納付税額)も毎年変動するのでは、と税理士目線では思ってしまいます。
税務署における税務調査先の選定ですが、これは統括国税調査官と言う管理者が行います。
税務署にはAI機能を実装した財務分析機能があり、統括国税調査官は主にこの機能を活用することで税務調査先を選定するのです。
税務調査専門税理士として断言しますが、同規模同業種の他者と比べて粗利益が極端に低かったり、
前述のように毎年の納付税額が決まって数万円という個人事業主の確定申告書についは、財務分析機能により税務調査の対象として真っ先に選定されることになります。
話は変わりますが、個人事業主に対する税務調査においては「事業専用割合」が必ずチェックされます。
個人事業主の方であれば、ご自宅や車両をプライベートだけでなく事業用としても使用している場合がほとんどでしょう。
実際に事業として使用しているのであれば、持ち家や車両であれば減価償却費や諸経費、賃貸物件であれば支払家賃など一定の割合を必要経費として計上することが出来るのですが、
使用実態がどうあれプライベートでも使用しており公私が明確に区分されていない場合には、税務調査において必要経費として100%認めてもらえることはあり得ない、と考えた方が良いでしょう。
財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。
LINE ↓友だち追加↓
税務調査情報をお伝えいたします
お気軽に友だち追加してください
Menu
- 事務所紹介

